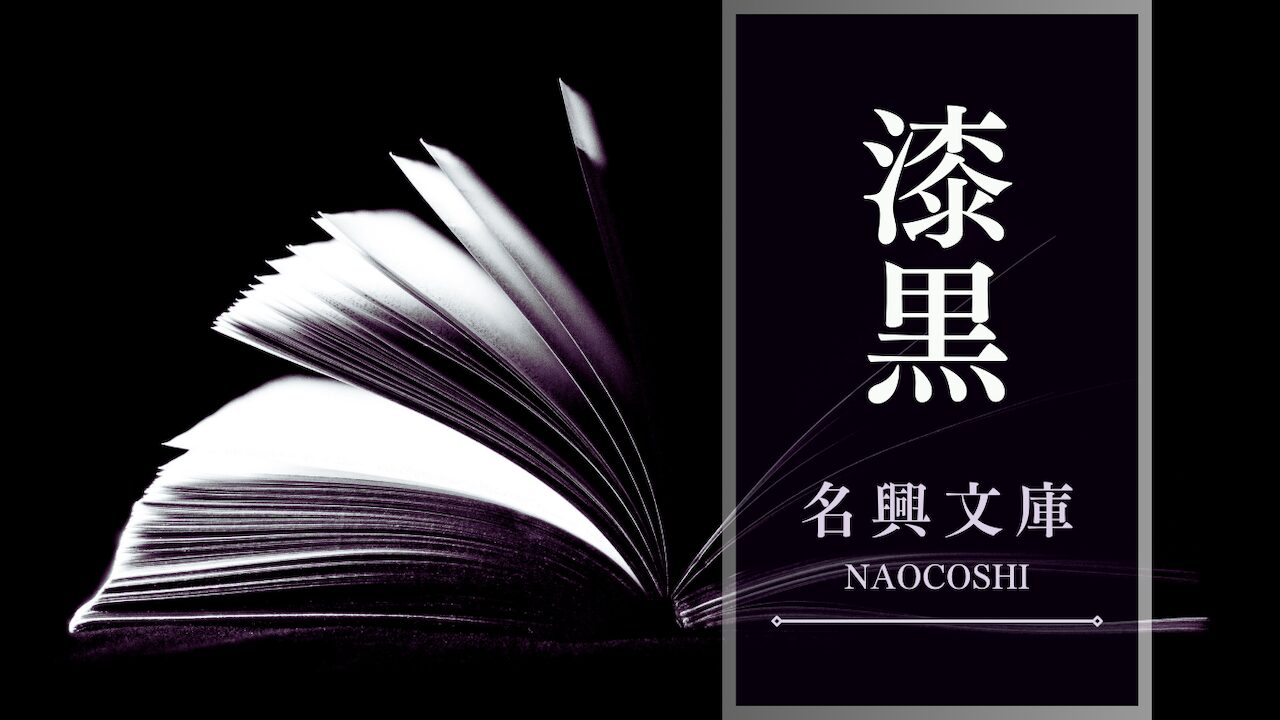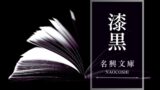- 所感
- 一次選評
- 『世界樹の世界/あるいは無限に脱皮する蛇の見た夢』|馬路まんじ
- 『一枚の絵』|中村実士与
- 『帰還』|中村実士与
- 『黄昏の空』|海木夜道
- 『古王の黒言』|海木夜道
- 『青涙の城』|海木夜道
- 『赤い森』|海木夜道
- 『アルテフォンの神話』|中村実士与
- 『トワイライトタウンの女王、双子のマレビトに命を下す事』|和田賢一
- 『ぐじん』|天方セキト
- 『闇夜茸と地獄の門』|StarFox
- 『災厄の古龍-その一記録-』|伏空紫央
- 『白紙画廊の夕べ 短編:『白紙画廊』』|ラウンド
- 『卒塔婆小町』|夢酔藤山
- 『貪欲のゾルーク』|和田賢一
- 『神剣の黒騎士』|ラウンド
- 『理を逸する』| 葛城騰成
- 『一瓶に流れる世界』|ラウンド
- 『メロモーニアの旅路』|NO SOUL?
- 一次選評:Creative Writing Space掲載作品
- 『霊薬』|かぶき六號
- 『ウーフニック』|称好軒梅庵
- 『時軸の竜と対の女神』|ムルコラカ
- 『夢よりの囁き』|茅杜弐 乃至真
- 『暗翼の飛艦』|茅杜弐 乃至真
- 『覚醒めよ、鉄の王よ』|茅杜弐 乃至真
- 『群島に吠ゆる』|茅杜弐 乃至真
- 『古龍と海人』|茅杜弐 乃至真
- 『出現《他》』|積 緋露雪
- 『かわずのゆめ』|百彪
- 『冬の騎士ネイヴァ』|理乃碧王
- 『100年の孤独』|天方セキト
- 『詩人が求めた永久の旅』|かぶき六號
- 『天突く雷塔』|月岡ユウキ
- 『渡しの巨人と最後の賢者』|ムルコラカ
- 『プロトの大地』|ひら やすみ
- 『フーア』|称好軒梅庵
- 『血色の薔薇庭』|ルーカスさん
- 『灰色の魔導師』|ルーカスさん
- 『神々とひとつの種』|かぶき六號
- 『黄金に輝く林檎』|ムルコラカ
- 『破滅の大釜』|ムルコラカ
- 『ヤルグェの誇りと赦し』|吾輩はもぐらである
- 『千年樹の試練』|吾輩はもぐらである
- 『ある町の素描』|昏野薄
- 『世界の闇・ディストール』|てぃえむ
所感
このたびは、【第01回】名興文庫-漆黒の幻想小説コンテストへご参加いただき、誠にありがとうございます! 一月度の締め切りを迎え、メール応募とCreative Writing Space様との提携を含め、計45作品のご応募をいただきました。この結果は、当初の予想を上回るものであり、関係者一同、大きな手ごたえを感じております。
今回は、各作品への『一次選評』として、短い所感をお伝えしております。これはあくまで第一印象に基づくものであり、最終的な講評や選評は、締め切り後に佳作および各賞の発表と共に行う予定です。
また、一次選評や参加者名をご覧になった方はお気づきかもしれませんが、今回のコンテストには既に書籍化の実績を持つ作家の方々が複数名参加されています。例えば、和田賢一先生、葛城騰成先生、称好軒梅庵先生、そして馬路まんじ先生など、お名前を拝見するだけでも多様な作風が期待されます。特に、馬路まんじ先生がいち早くご応募くださり、趣旨を的確に捉えた作品を寄せてくださったことには驚きとともに深い感謝を覚えました。著名な先生方の作品が一堂に会することで、今回のコンテストの価値は一層高まり、参加者の皆様にとっても貴重な機会となることでしょう。
本コンテストの意義として、ライトノベルやWeb小説の枠を超えた表現の自由や、異なるスタイルの対比を可視化することが挙げられます。今回、多くの作品が集まったことで、幻想性や壮大性がいかに多様な文体で表現されうるか、その幅広さを確認できました。「幻想小説とは何か?」と模索される方にとっても、今回の応募作品群は大いに参考になるはずです。単一の表現に収束せず、幅広いアプローチが存在していることが、このコンテストの大きな魅力となっています。
今後、八月末の締め切りまで、計七回の所感を発表できることを楽しみにしております。皆様のご応募が、コンテストをさらに充実したものにしていくことでしょう。引き続きのご参加を心よりお待ちしております!
一次選評
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『世界樹の世界/あるいは無限に脱皮する蛇の見た夢』|馬路まんじ
壮大なスケールで描かれる世界樹の物語。流れるような読みやすい文体ながらも、人の営みが繰り返されるなかで、変わることのない世界樹が抱える問いが印象的です。その問いに応えるのが、大地の地脈なのか、それとも知恵の象徴たる蛇なのか。静かでありながらも、深く考えさせられる作品でした。
『一枚の絵』|中村実士与
美しい風景画の沼、しかしその深奥は誰も知らない──そんな神秘的な雰囲気が漂う物語です。湖や泉から現れる妖精たちは魅力的ですが、彼らに誘われた者たちの運命は果たしてどうなるのか。幻想的でありながら、ショートショートのような軽やかさも持ち合わせた作品でした。
『帰還』|中村実士与
異世界の一幕を描いた作品。勇者というテーマはよく知られた異世界ファンタジーの要素ですが、それをどの視点で捉えるかで作品の印象が大きく変わります。今回は神話的な勇者のイメージが強く、読み手によって評価が分かれるかもしれません。
『黄昏の空』|海木夜道
少女の自我の探求を描いた物語。テーマが明確で、イメージも伝わりやすいのが魅力です。会話文が多いため、伝統的な文体とライトな文体の中間にあるような印象を受けました。読者の好みによって評価が分かれる部分もありますが、それだけ多くの人に届く作品とも言えるでしょう。
『古王の黒言』|海木夜道
恐ろしいシーンの迫力がもう少し強調されてもよかったかもしれません。また、物語の舞台となるロケーションをさらに際立たせることで、「意志を受け継ぐ」というテーマがより明確になったように思います。会話文のバランスについては、物語をどの方向へ持っていくか、という点で試行錯誤が感じられました。
『青涙の城』|海木夜道
物語の前半に対し、後半の展開がやや駆け足な印象を受けました。説明を加えるか、あるいは読者が直感的に納得できるような構成を強めることで、より完成度が増すかもしれません。作品の骨格はしっかりしているので、どの要素を強調するかが鍵になりそうです。
『赤い森』|海木夜道
幻想的な雰囲気がありつつも、赤い森が何を象徴するのか、もう少し断片的なヒントを散りばめてもよかったかもしれません。読者が想像しながら読み進められるような構成にすることで、さらに味わい深い作品になりそうです。
『アルテフォンの神話』|中村実士与
一つ一つは断片的なエピソードですが、全体を通して読むと一つの神話として完成する構成が魅力的です。ただ、俯瞰的な視点が強いため、読者の想像力によって印象が変わる作品かもしれません。個人的にはこの試みがとても面白く感じられました。
『トワイライトタウンの女王、双子のマレビトに命を下す事』|和田賢一
壮大な世界観の序章といった印象の作品です。ライトノベル的な文体ながら、異世界の驚きや広がりがしっかりと感じられます。またタイトルの「トワイライトタウン」はとてもライトみが強いですが英語解釈では自然に受け入れられる表現であり、ここは感覚が分かれるところでしょう。物語としては『起こり』に終始している構成です。
『ぐじん』|天方セキト
人には完全には理解できない異なる存在と、その終焉を描いた物語。壮大な営みの終焉と、密接に関わりながらも決して一つにはなれないもの──その対比がとても印象的でした。簡単に言葉にできない表現が、作品の奥深さを増しています。
『闇夜茸と地獄の門』|StarFox
広がりのある世界観を感じさせる物語ですが、前半の説明がやや多く、物語の流れを阻害している印象を受けました。また、「闇夜茸」と結末の関連性が薄いため、全体としてのまとまりがやや弱いかもしれません。ただし、大きな背景世界があることはしっかり伝わってきました。
『災厄の古龍-その一記録-』|伏空紫央
隠蔽された歴史と、そこから現れる真実、そして再び訪れる災厄──。ライトノベル的な文体でありながら、伝説の再来を重厚に描いている作品でした。物語の進行が非常にスムーズで、読者を引き込む力があります。
『白紙画廊の夕べ 短編:『白紙画廊』』|ラウンド
芸術や美をテーマにした物語。白紙画廊の「白紙」とは何を指すのか、それが多様な解釈を持つ点が魅力的です。個人と共有されるものが絡み合いながらも、必ずしも一致しない──その構造が巧みに描かれています。
『卒塔婆小町』|夢酔藤山
『卒塔婆小町』をテーマに、魂だけが残った先の苦悩を描いた作品。苦しみが外に伝わることなく、永遠に閉じ込められる様子が、無限の時間とともに表現されていました。テーマが非常に強く、読後に余韻が残る作品です。
『貪欲のゾルーク』|和田賢一
大きな物語の始まりを予感させる作品。背景の説明もしっかりしており、読者を引き込むワクワク感があります。ただ、やはり「起」にとどまる物語であるため、次の展開が気になるところです。
『神剣の黒騎士』|ラウンド
一見、ライトノベル的な終末の断片に見えますが、冒頭の『男のようでもあり女のようでもある』という表現が、黒騎士の神ウォーダン・ヒルドに帰結しています。ウォーダンはオーディンの別名であり、ヒルドはしばしばヴァルキリーの名前に用いられる『戦い』を意味する、しかし女性名に用いられている言葉であり、これが背景を色々と想像させる物語です。しかし、造語とルーツのある言葉の組み合わせの難しさもまた出ていますね。
『理を逸する』| 葛城騰成
純粋な心を持つ者が世界と語らう中で、時代の終焉を迎える物語。人の理と世界の理が必ずしも一致しないというテーマが深く、幻想性と人間の在り方が巧みに描かれています。細部をもう少し掘り下げると、さらに厚みのある作品になりそうです。
『一瓶に流れる世界』|ラウンド
錬金術的な実験をする魔女と子供たちの会話を通じて、「時間」というテーマを考えさせられる物語。子供と大人の時間の違い、その不思議さが温かみのある筆致で描かれていました。
『メロモーニアの旅路』|NO SOUL?
不思議な楽人・旅人メロモーニアの物語。独特の世界観が広がるなかで、囁かれる言葉の意味を考えさせられます。幻想小説としての壮大さと、物語世界への引き込みが見事でした。
一次選評:Creative Writing Space掲載作品
*順不同・敬称略とさせていただきます。
『霊薬』|かぶき六號
若さゆえの勢いで突き進むことができるのは素晴らしいことですが、その中に迷いが生じると、一気に状況は変わります。全てを失い、振り返っても取り返せる方法が分からないまま手遅れになってしまうことも。しかし、それを単に「愚か」と片付けることはできません。誰もが通る道だからです。本作は、多様な文体が活きるコンテストの中で、個性的な一作となっています。
『ウーフニック』|称好軒梅庵
ボルヘスの『幻獣辞典』に登場する「足萎えのウーフニック」をベースにした幻想的な作品……というより詩のような趣があります。ユダヤの伝承に起源を持つこの存在はとても興味深いものです。これを「佯狂者」に関連付けて考えることもできますが、そもそも私たちはしばしば精神的に「死んでいる」状態にあるものです。自分の役割を自覚すること、あるいは錯覚することは、時にそれ自体が死に等しいものだからかもしれません。
『時軸の竜と対の女神』|ムルコラカ
多くの人の心の中に「竜」という存在は宿っています。それは幻想の象徴とも言えるものですが、その本質とは何なのでしょうか? おそらく、それは過去のある時代と魂に刻まれた記憶のようなもの。この物語は、世界の変遷とともに人々の心に生き続ける「竜」の存在を描いているのかもしれません。
『夢よりの囁き』|茅杜弐 乃至真
どこか妖しく艶やかな暗さが漂う物語。最後の一文は、それまでの流れからすると少し意外な展開に思えます。しかし、だからこそ読者の想像を刺激するものになっています。それは諦めなのか、それとも希望なのか。読者によって解釈が分かれそうです。
『暗翼の飛艦』|茅杜弐 乃至真
ライトノベル的なファンタジー作品の一部といった印象ですが、描写や名称にもう少し統一感があると、より引き込まれる作品になるかもしれません。物語の焦点が複数存在しており、短い文章の中ではやや散漫な印象を受けます。1000字という制約の中で大きな物語の一部を切り出す場合、選択と集中がより重要になってきます。また、固有名詞の統一感を意識すると、さらに洗練された作品になるでしょう。
『覚醒めよ、鉄の王よ』|茅杜弐 乃至真
この作品は「選択と集中」がしっかりとできており、一つの時代の終焉と、それに伴う破滅と破壊が描かれています。タイトルの『覚醒めよ』から始まり、『夜が明けることはなかった』という結末へと至る構成は、物語に皮肉と哀切を加え、読後の印象を強めています。
『群島に吠ゆる』|茅杜弐 乃至真
「禁足の地」や「忌み地」に足を踏み入れたとき、何が起こるのか。そうしたテーマを扱った作品です。よくまとまった物語ですが、もう少し細部の描写や幻想的な要素を強調すると、さらに魅力的になりそうです。1000字という制限の中での構成はしっかりしています。
『古龍と海人』|茅杜弐 乃至真
物語としてはまとまっていますが、ライトノベル的な断片のような印象もあります。そのため、なぜこの展開が必要なのか、あるいは過去の伝承との繋がりを強めると、より深みのある作品になりそうです。冗長なセリフや説明よりも、作中に伝承や神話を組み込むことで、物語全体の整合性を高める工夫が求められます。
『出現《他》』|積 緋露雪
古典文学を思わせるような統一感のある文体で描かれた物語。物語の核心となる「出現」が、破滅なのか、それとも再生なのかは明言されておらず、読者の想像に委ねられています。これはまさに、一抹の自由が残された大いなる瞬間を切り取った作品とも言えるでしょう。
『かわずのゆめ』|百彪
夢を見ているのは誰なのか? また、「かわず」は本当に夢を見るのか? 郷愁を感じさせる描写と共に幻想の世界へと読者を引き込んでいく物語です。しかし、それが本当に幻想なのかどうかは、読み進めるうちに疑問が生まれてきます。私たちの現実もまた、時に曖昧なものですから。
『冬の騎士ネイヴァ』|理乃碧王
一見するとライトノベルの一節のようですが、最後まで読むと、これは季節の移ろいを擬人化した伝承のようにも感じられます。我々の文化で言えば、お神楽のようなものに近いでしょう。そういえば、天気予報でも季節を擬人化した表現を見かけることがありますね。「ライト」という言葉を高尚に解釈するならば、親しみやすさを重視したカジュアルな形にすることとも言えます。
『100年の孤独』|天方セキト
冒頭と結末が少し説明不足に感じられました。定命の者と不死の者、戻らない童心や純粋さを思うとき、どちらがより多くの哀しみを抱えることになるのでしょうか。変わらないものがあったとしても、それが救いになるとは限りません。ファンタジーの世界観を使うことで、このような対比をより鮮明に描くことができます。
『詩人が求めた永久の旅』|かぶき六號
壮大な旅の果てに、詩人が見出したものは、愛する者の瞳に映る自分自身だったのでしょうか。得難い永遠の価値とは、意外にも身近な場所に存在するものですが、その場所を豊かにすることは容易ではなく、ときには長い旅を経る必要があるのかもしれません。
『天突く雷塔』|月岡ユウキ
技術が失われつつある現代において、非常に象徴的な物語です。かつて国語の教科書に掲載されていた岡野薫子さんの『桃花片』を思い起こさせます。我々には、時を超えて見守る先人の存在がありがたく、幻想小説においてはしばしばその憧れが描かれるものです。
『渡しの巨人と最後の賢者』|ムルコラカ
「ひとつの世界の終わり」から次の世界へと橋渡しする物語です。細やかな描写が物語世界の想像をかき立て、過去だけでなく未来にもつながる要素を持っている点が魅力的です。
『プロトの大地』|ひら やすみ
聖書のエピソードとも共鳴する内容ですが、しっかりと結末まで描かれています。短いながらも深い示唆に富んだ物語で、読み手の心に残るでしょう。同様の話は、マヤ・アステカ神話の「木の人」の伝承にも通じるものがあります。我々もまた、未来の人々からどのように見られるのか、考えさせられます。
『フーア』|称好軒梅庵
フーアはスコットランドの水にまつわる怪異か、それとも「WHO are YOU?」という問いかけでしょうか。詩のようでありながら、小説としても読める作品です。「醜い」とされる存在を描きつつ、それが本当に醜いのかを問い直す構成が印象的でした。我々自身も、果たして何者なのかを問われれば、怪しいものかもしれません。
『血色の薔薇庭』|ルーカスさん
文字数の範囲内で物語としてまとまっていますが、人物の描写に終始しており、舞台となるオブジェクトの存在感が薄くなっているのが惜しまれます。むしろ、この呪いの起源に焦点を当てた方が、より深みのある物語になったかもしれません。
『灰色の魔導師』|ルーカスさん
こちらも人物の描写が中心となっていますが、幻想的な要素が控えめになっており、やや単調に感じられます。翻訳の影響もあるかもしれませんが、作者が英語での執筆を得意とするならば、原文の方がより魅力的に感じられる可能性があります。ライトノベル的な構成や表現が根底にあるのも特徴的です。
『神々とひとつの種』|かぶき六號
前半は「猿から人へ」の進化論を思わせる展開ですが、最後には異なる世界へと旅立っていきます。我々人間も自然の一部ですが、この物語のように調和しながら進むことができるのでしょうか。
『黄金に輝く林檎』|ムルコラカ
多くの神話に登場する黄金の林檎ですが、この物語では独特な生命の循環が描かれています。落葉帰根、あるいは還樹という概念を、詳細な描写で見せる点が印象的でした。
『破滅の大釜』|ムルコラカ
神々の時代が終わり、人の時代が訪れる理由については意外と語られることが少ないものです。この物語では、過ぎ去った豊かな時代を懐かしみながらも、飢えを抱えて歩み続ける人間の姿が描かれています。
『ヤルグェの誇りと赦し』|吾輩はもぐらである
人物に焦点を当てた物語ですが、通常の英雄譚とは一線を画しています。美化された英雄譚ではなく、秘められた醜悪さと、それを凌駕する崇高な孤高さが描かれている点が際立ちます。この物語にさらに幻想性を加えるのは、むしろ惜しいかもしれません。
『千年樹の試練』|吾輩はもぐらである
『ヤルグェの誇りと赦し』の前日譚としても読める作品です。天から与えられたものをそのまま受け取るのではなく、独自の形にして返すことの意味が描かれています。演出や共感をもう少し強調してもよかったかもしれません。
『ある町の素描』|昏野薄
この町は長い逃避の果てにたどり着くものなのか、それとも煉獄や忘却の地なのか。明確な答えはありませんが、どんな場所にも安らぎを見出す者はいるものです。それは夢想ではなく、一瞬の輝きとして存在するのかもしれません。
『世界の闇・ディストール』|てぃえむ
筆者の物語世界の一端を垣間見ることができる作品です。ライトノベル的な文体と演出ながらも、「世界の闇」は普遍的であり、作中で語られるように、終焉と始まりの狭間にあるものなのかもしれません。そしてそれは、我々の心の内にも通じるものがあるでしょう。